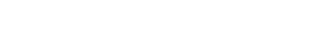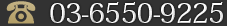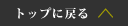本日は気になる記事を見つけましたので、ご紹介させて頂きます。
是非、一読下さい!
suumoジャーナル 住宅ジャーリスト 山本久美子さんのコラムです。
国土交通省は、マンション管理実態に関する「マンション総合調査」を5年ごとに行っており、平成25年度の結果を公表した。住活トピックとしては、そのなかでも、マンション内のトラブルについて詳しく見ていくことにしよう。
マンションのトラブルトップは、居住者間の行為・マナー。なかでも「生活音」が目立つ
平成25年度の「マンション総合調査」は、昨年12月、全国の3643の管理組合と7484の区分所有者を対象に実施し、2324の組合と4896の区分所有者が回答したもの。
過去一年間のマンション内トラブルの発生状況については、「特にトラブルは発生していない」が26.9%で、前回の22.3%より4.6ポイントアップ。全体的にトラブルの発生状況は減る傾向にはあるが、相変わらず「居住者間の行為、マナーをめぐるもの」によるトラブルが最多の55.9%で、過半数を占めている。次いで、「建物の不具合にかかわるもの」(31.0%)、「費用負担にかかわるもの」(28.0%)の順だ。
マンションの属性別で見ると、「居住者間の行為、マナー」によるトラブルについては、総戸数規模が大きいものほど発生状況が高まる傾向にあり、「建物の不具合」や「費用負担」によるトラブルは、完成時期が昭和45年~54年などの古いマンションで高まる傾向が見られた。
では、具体的にどういったトラブルが発生しているのか?
居住者間の行為、マナーでは「生活音」が34.3%と最も高く、「違法駐車」(24.7%)、「ペット飼育」(22.7%)、「共用部分への私物の放置(18.4%)、「違法駐輪」(15.4%)などが続く。
建物の不具合では「水漏れ」18.8%、「雨漏り」12.2%と、水のトラブルが多く、費用負担では「管理費等の滞納」が27.2%と突出して高い。
ほかに、管理組合の運営のトラブルで「役員または専門委員の人材不足」(11.4%)などが目立つ。
こうしたトラブルはどのように対処したのだろうか?
「管理組合内で話し合った」が69.2%と最も多く、次いで「マンション管理業者に相談した」が48.0%となっている。
マンションコミュニティがトラブル回避には重要
マンションは同じ敷地や建物を共同で利用する、共同生活が基本。居住している世帯数が多くて多様になるほど、暮らし方や価値観の違いで、相手の行為を不快に感じることも出てくるだろう。
特に、生活音や駐車場・駐輪場のマナーなどは、この程度なら問題ないだろうと思ったことが、他人から見れば許容できないレベルということも多い。トラブルの当事者同士だけで解決しようとすると、感情論になってしまい、かえってこじれることもある。
そこで重要になるのが、マンションコミュニティだ。トラブルの芽は早く摘むに限る。トラブルが発生したら、トラブルになるレベルを整理して、注意喚起を促すなどのマンション内の自浄能力が求められる。それを担うのが管理組合だが、年に1回の総会などの定例行事だけではコミュニティ形成は難しい。
最近の新築マンションでは、当初一定期間は外部のプロに委託して、頻繁にイベントを行い、マンションの居住者同士が触れ合える機会をつくろうという動きが出ている。
どういった人が住んでいるのかが分かるだけでも、生活音への配慮の仕方が変わるし、他人への迷惑の考え方も変わる。さらに、良好なコミュニティは、トラブルを話し合いで解決しようとする自浄能力も高めることになる。
もちろん、引越したら上下階や隣室へ挨拶をしたり、マンション内のご近所づきあいを大切にすることなども、トラブル回避には有効だ。互いへの配慮がなければ、共同生活は上手くはいかない。
今回の調査結果では、マンション居住者(世帯主)の過半数(50.1%)が60歳以上となるなど、居住者の高齢化も浮き彫りになった。居住者の高齢化は、災害時の救助や管理組合の役員の人材不足などの問題につながることにもなり、ますますマンション個々の事情に応じた柔軟な対応が求められるようになる。それを可能にするのは、やはり良好なマンションコミュニティではないだろうか。