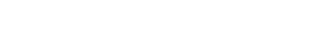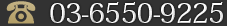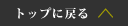本日は気になる記事を見つけましたので、ご紹介させて頂きます。
情報が多い時代、目を養う事が非常に大切なんです。
弊社も今まで以上に、誠実にやって行きたいと思います。
suumoジャーナル 住宅ジャーリスト 山本久美子さんのコラムです。
公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会によると、不動産広告の悪質な違反に対する処理(厳重警告または違約金課徴)事案のうち、インターネット広告の占める割合が年々増加しているという。なかでもおとり広告が目立つというのだが、数多くの不動産広告からどうやって見分けたらよいのだろうか?
インターネット広告の悪質な違反が年々増加
首都圏不動産公正取引協議会は、「不動産の表示に関する公正競争規約」(不動産広告のルール)などを適切に運用するための不動産業界の自主規制機関のひとつで、関東甲信越地域を管轄する公益社団法人だ。
同協議会では、不動産広告を常時監視し、表示規約に違反する広告を行った不動産会社に対して、必要な調査をした上で、不動産会社から事情を聞き、再び同様の不当表示をしないよう警告したり、違反内容によっては違約金を課徴している。
同協議会が平成25年度に調査した1782物件のうち、ポータルサイトに掲載されている物件情報などのインターネット広告は701物件(39.3%)と全体の4割程度。しかし、668物件あった賃貸物件に限って見ると、インターネット広告が556物件(83.2%)と圧倒的に多くなっている。
調査の結果、不動産広告として表示すべき項目を満たしていない、あるいは周辺施設の表示は物件までの道路距離を表示しなければならないところを分数表示にしているなど、比較的軽微な違反について「注意」勧告をしたのは、103件。新聞の折り込みチラシなどが圧倒的に多いという。
一方、おとり広告や不当表示など悪質な違反については「警告」(35件)や「違約金課徴」(58件)を行った。こうした悪質な違反は、インターネット広告での違反が目立ち、「警告」27/35件、「違約金課徴」52/58件となっている。
インターネット広告において違約金が課徴されるなどの悪質な違反は、年々増加する傾向にあり、平成25年度では89.7%を占めるに至っている。
実際とは異なる広告でユーザーを集めるのが狙い
悪質な違反とはどういったものなのか、同協議会のホームページにまとめられた違反事例で具体的に見ていこう。
「おとり広告」では、既に契約済みであるにもかかわらず広告の掲載を長期間行ったり、実際には物件の資料がないのに広告をしていたり、実在した物件の賃料などを安くして広告していたりといった事例が目立つ。
また、「不当表示」の広告ではいくつかの傾向がみられる。
まず、媒介(仲介)物件であることを記載せず、売主であるかのような広告になっているが、契約が成立すると仲介手数料が発生する事例。キャンペーン賃料のみを記載して、本来の賃料を記載していない事例。保証料や保険料、鍵交換費用などの諸費用を記載していない事例。いずれも、本来必要な額より安く見えるように広告したものだ。
次に、土地に路地状部分を含んでいるのにそれを記載していない事例、土地面積に私道を含んでいた事例など、実際より広く見えるように表示したり、間取りや設備を正しく記載していない事例、実物と違う室内や外観写真を掲載する事例など、実際のものより良い物件であるように広告したもの。
さらに悪質な事例では、土地の販売であるのに勝手に新築住宅として広告したり、駅徒歩60分なのに15分と記載したり、延伸計画がないのに物件の近くに新しく最寄駅ができると記載したりと、ユーザーをだまそうとするあきれる事例もあった。
相場より明らかに安い物件は疑う余地がある
ではどうしたら、悪質な違反広告を見分けることができるのだろうか。
おとり広告には、相場より安い物件を掲載することでユーザーを来訪させ、ほかの物件を紹介して契約させるためのものも多い。合理的な根拠がないのに相場より安い物件というのは、実際にはめったにないと考えておくのがよいだろう。数多くの不動産広告を見比べて、価格や賃料の相場を把握することはとても重要。一般的に必要とされる価格や賃料以外の諸費用などを押さえておいて、その有無を確認するのも有効だ。
また、来訪してみたら、何かと理由(難癖)をつけて広告した物件を見せてもらえない場合も、疑うポイントになる。「あの物件には実はこんな不利な条件があるから」などと言われた場合、その条件によっては広告に記載していないと広告ルールに違反する可能性がある。広告のルールは、原則として不利な条件も広告に記載することになっているからだ。「昨夜成約してしまった」と言われた場合、本当に成約していた物件なら広告物件の資料などが手元にあるはずなので、気になるならそこまで確認する手もある。
不誠実だと思ったら、そうした不動産会社からは、物件を紹介してもらわないほうがよいだろう。ただし、こうした不動産会社は業界内の一部にすぎない。同協議会の上席調査役佐藤友宏さんは、「当協議会管轄の関東甲信越(1都9県)には、約5万3000社の不動産事業者がいます。そのうちの58社が違約金課徴の措置を受けましたが、それはわずかな事業者であるということです」とも指摘した。
インターネットの違反広告を減らすために、同協議会は「ポータルサイト広告適正化部会」を平成24年3月に発足させ、SUUMOなどのポータルサイトで、平成26年4月から違反物件の情報を共有するという発表が同部会からなされた。それによって違反広告が減ったとしても、借主や買主自身が、物件情報を見比べて冷静に判断することが、トラブル防止の最善の策だ。